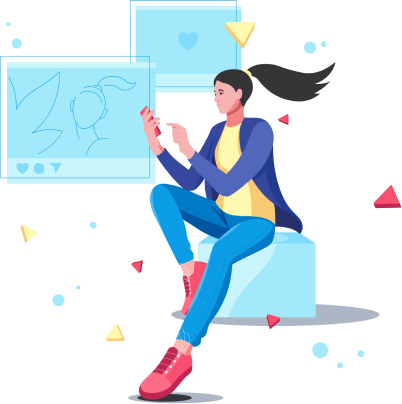ブラウジング、 あるいはライティングにも大切な、 ディスプレイの角度。 当ブログでは以前、 パソコンに向かう姿勢を改善すべく、 PCの角度を自由に調節できるMacBook用スタンドを紹介しました。
ところが、 MacとiPadを併用するスタイルが多い僕からすれば、 「iPadに特化したスタンドで良いモノはないだろうか…?」 と。 すなわち、 iPad版 「Majexstand」 のようなものがあればなあ…と思って止まなかった訳です。
そこに、 オシャレかつ機能性抜群で評判の高いノートパソコン用スタンド 「MOFT」 のタブレット・スマホ版がリリースされるとの一報が。 その名も 「MOFT X」 。
これを試さない手はない! と思っていたところに、 運よくMOFT様から 「MOFT X」 シリーズのサンプルをご提供いただいたので、 早速使用してみました。
タブレット版 「MOFT X」 の大きな特徴は 「コンパクト」 「多機能」 「デザイン性」 の3点に集約されます。
「コンパクト」 ー iPadの良いところを邪魔しない

「MOFT X」 を取り付けた iPad Pro 12.9 インチを横から見た様子。
さて、 写真は僕の愛用するiPad Pro 12.9インチに 「MOFT X」 を取り付けて、 横から見た様子です。 タブレット用 「MOFT X」 は厚さが最大 3.7 mm(詳しいスペックは後述)と驚くほど薄いので、 取り付けてもiPadの機能性を損なうことはありません。

「MOFT X」 を取り付けた状態でライティングしても、 基本的にガタつくことはない。
筐体の中央に 「MOFT X」 を貼り付ければ、 iPadを平置きした状態でも安定してライティングをすることができます。
コレって意外にすごいことで、 iPadに貼り付けるタイプのスタンドは、 しばしば平置きで使用するとガタついてしまうという欠点を持っているので、 「薄さ」 でこの点をしっかりカバーできている 「MOFT X」 にはそれだけで固有の価値があるように思えるのです。
iPadの軽さを活かす作り

通常サイズの 「MOFT X」 は文庫本より少し軽いくらいの重さ。
iPad Pro 11インチが 468g、 最新のiPad Pro 12インチが 631g(Wi-Fiモデル)なのに対し、 通常サイズの 「MOFT X」 は 137 g(iPad mini用の小サイズ版は 87 g)と非常に軽く、 iPadの利点でもある軽量性をしっかり活かすつくりになっているのもポイントです。
一般的な文庫本の重さが 150g 前後なので、 「MOFT X」 はそれよりも少し軽いくらいの重量感になります。

「MOFT X」 をつける前後で、 iPadの使い勝手に違和感が生じないのは称賛されるべき点であろう。
このように、 「MOFT X」 はそれ自身が過度に主張することなく、 iPadの魅力をしっかり引き立てるように設計されているのです。 その為、 「MOFT X」 をつける前後でiPadの使い勝手にネガティブな変化が生じたことは今のところ全くありません。
広告/Advertisement
「多機能」 ー 縦横6段階の角度調節
「MOFT X」 はそのコンパクトな見た目からは想像もつかないほど高い機能性を持っています。 最たるものは縦横3段階ずつ、 合わせて6段階の多段階調節ができる点でしょう。
横は3段階の角度調節ができる

「MOFT X」 をよく見ると、 わずかに凹凸がついていると同時に、 複数の折り目があることがわかります。 実は 「MOFT X」 にはマグネットが内蔵されていて、 折り目を使って 「MOFT X」 を変形させることで、 iPadを様々な角度で立てかけることができるようになるのです。

例えば 「MOFT X」 をこのように折り込むと…

およそ60度でiPadを立てかけることができます。 Web上で記事を読んだり、 Youtubeを閲覧したりと、 ブラウジング作業にはこの角度が最も適しています。

続いて、 折り込む位置をこのように変えると…

先程よりも角度が浅くなりました(およそ40度)。 このように、 折り込み方でスタンドの形を自由に変形できるので、 iPadを立てる角度の調節ができるというのが 「MOFT X」 の強みです。

最も浅い位置でiPadをたてた様子。 Apple Pencil との相性が良い。
一番浅い角度は、 思いついたことをメモしたり、 イラストを描く際に適しています。 ただし 「MOFT X」 を貼る位置によっては、 ライティングの際にiPadがガタつく場合もあるので注意が必要です。
![]() 九条ハル
九条ハル
公式によればMOFT Xは 「500回の貼り直しが可能」 とのことだから、 貼る位置を間違えちゃっても安心だね!

山の一部を内側に折り込むことで、 最も浅い角度にスタンドが調節される。
裏側は、 先程の状態(40度)で山折りになっているところの一部分を内側に折り込んだ構造になっています。 折り目がしっかりついているのとマグネットを内蔵していることにより、 くっ付けた際に 「パチっ」 という音と確かなフィードバックが返ってきます。 そのためー見複雑そうでも、 案外感覚的に組み立てられるのが評価できるところです。
縦も3段階で角度を変えられる

縦置きはタイムラインを確認したり、 縦に長いWeb記事を読むのに最適。
iPadの横置きができるスタンドは多いですが、 縦置きもできるスタンドとなると珍しいのではないでしょうか。 iPadを縦置きした状態で使うのは、 タイムラインを一覧で確認したり、 縦長になりがちなWeb上の記事をチェックするケースと非常に相性が良いです。

中間の40度。 最近はYoutubeを開いて、 動画を見ながらコメントを読んで楽しむのがお気に入りです。 インターネットは縦スクロールが基本ですから、 その性質上縦置きだと得られる情報量が格段に多くなるというメリットがあるんですね。

IMAGE BY MOFT X
以上を含めて、 縦横計6段階の調節が可能になっています。
ポイントは、 変形の際にいちいち裏面を見なくても感覚的に調節ができる点にあります。 地味かもしれませんが、 「パッと一瞬で角度を変えたい」 と思っている人(僕)にとってはとてつもなく大きなメリットになります。
簡易 「バンカーリング」 としても使える
僕はディスプレイの大きさに惹かれて、 12.9インチのiPad Proを愛用しています。 ところが、 大型かつフラットな形状をしている為、 手で持ったまま長時間使うとすぐに疲れてしまうという欠点がありました。

物理的な 「とっかかり」 ができるコトで、 大型のiPadをでも手持ちが楽になる。
オフィシャルな使い方ではありませんが、 「MOFT X」 をバンカーリングのように物理的な取っ掛かりとして使うことができます。 こうすることで、 バンカーリングの使い勝手には及びませんが、 簡易的な取手としては十分利用することができます。 おかげで、 大型のiPadでも手持ちで使用するのが格段楽になりました。

iPadを手持ちで使ったり、 そのまま持ち歩く機会が増えた。
今まで見てきた通り、 お伝えしたいのは 「MOFT X」 がiPadのコンパクトさを保ちながら、 純正の Smart folio より高い機能性を持つ優秀なスタンドであるということです。 続いて、 その性能を保証するデザイン性について見ていきましょう。
「デザイン性」 ー実力を語る相貌

プロダクトの魅力を伝える上で、 「見た目」 というのは一番に挙げても良いくらい大切な要素です。 我々は何事も 「カタチ」 からその第一印象を形作る生き物です。 デザインがしっかりしている、 それだけで見る人に 「実用性」 「頑丈さ」 「高級感」 等様々な印象を与えることができるのです。
そうした信条を踏まえて 「MOFT X」 を見ると、 スタンドとしての頑丈さ、 そして品質の高さを伺わせるような考えられたデザインに仕上がっているのがわかります。

「MOFT X」 はファイバーグラスを用いた外面と、 スエード調で触り心地の良い内面からなっています。 色合いもダークにまとめられていて、 スペースグレーのiPad Proには違和感なく溶け込み、 逆にシルバーのiPad(Pro)ではアクセントとして映えるつくりになっています。
タブレットサイズに合わせた2サイズ展開

タブレット版 「MOFT X」 には大きさに合わせて通常サイズと 「mini」 サイズの2種類がある。 一番右はスマホ用 「MOFT X」 。
一番左は12.9インチiPad Proに通常サイズの 「MOFT X」 を取り付けた様子。
タブレット用の 「MOFT X」 には大きさに合わせて通常サイズと 「mini」 サイズの2種類が用意されています。

通常サイズは、 9.7インチ〜11インチiPad(iPad Pro)や12.9インチのiPad Proに使うことができます。 12.9インチに取り付けると、 上の写真のように十分な余白があるので、 干渉を気にせず貼り付けることができました。

「mini」 サイズはiPad miniにピッタリ。
「mini」 サイズはその名の通り iPad miniにピッタリ合う大きさになっています。

「MOFT X」 の裏面。 黒い部分がゴム質の粘着シートになっている。
裏面の粘着シートはMOFT公式によれば500回の貼り直しが可能なので、 貼り付ける際に失敗を気にしなくて済みます。
広告/Advertisement
タブレット用 「MOFT X」 のレビュー総括
以上、 「MOFT X」 のタブレット版について簡単にレビューさせていただきました。 ポイントをまとめると、 こんな感じ。
- 薄型なので裏面に貼っても機能性が落ちない
- iPadの軽さを損なわない設計
- 純正より便利! ?縦横合わせて6段階の角度調節
- 感覚的に組み立てられるのがラク
- 簡易バンカーリングとしても使える
- 上質な生地、 iPadに溶け込むデザイン

iPad miniに 「MOFT X」 を取り付けた様子。
次回は、 本記事で紹介したタブレット用スタンド 「MOFT X」 のスマホ版についてレビューしていきます。 タブレット版とは異なる特徴や、 スマホならではのポイントも見つかったので、 その辺りを中心に扱っていきます。
SOURCE




 Quest 編集部
Quest 編集部